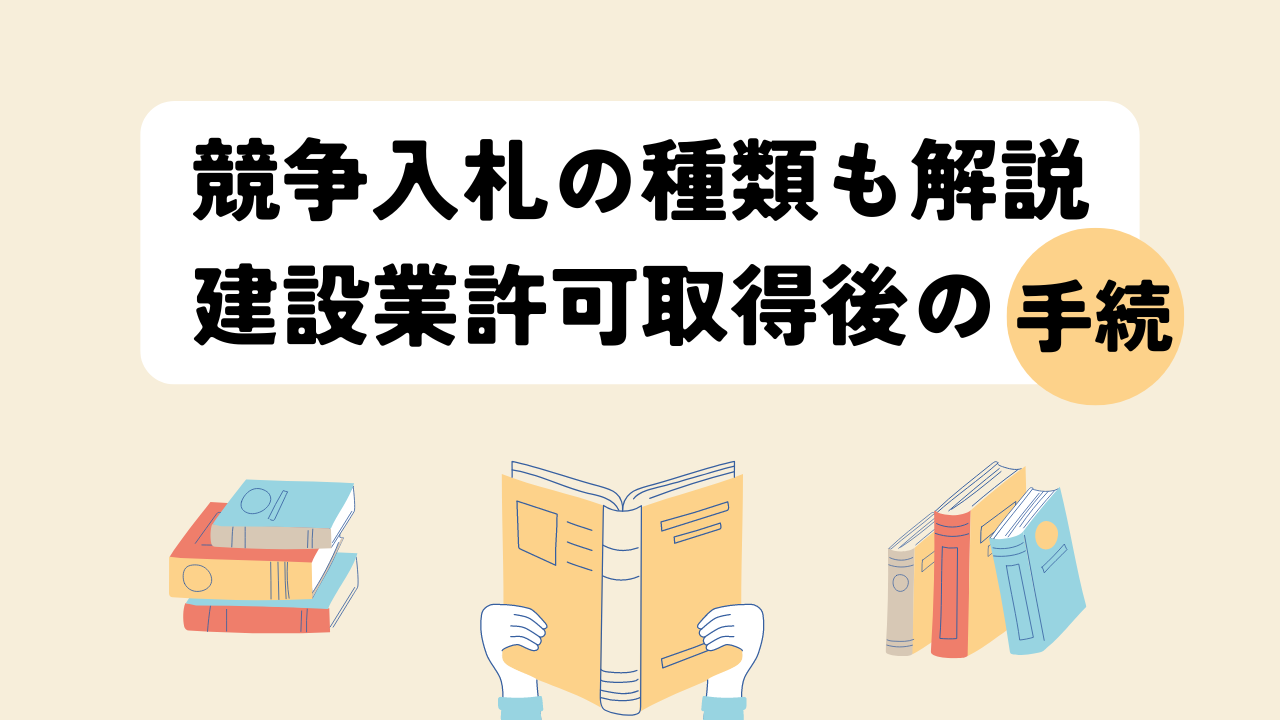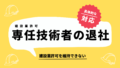公共工事の入札資格
公共工事の入札に参加するには、入札参加資格を取得しなければなりません。
公共工事の入札に参加するには、次の要件を満たす必要があります。
(1)建設業許可を取得していること
(2)経営事項審査を受審していること
入札参加資格の審査では、経営状況や経営規模、技術力や客観的事項について審査が行われて、点数化されて格付けされます。
入札参加資格は、発注する機関ごとに申請する必要があります。審査に合格すると、入札参加資格者名簿に登録されます。
(3)税金の未納がないこと
(4)欠格要件に該当しないこと
公共工事の入札の種類
公共工事の入札には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3種類があります
一般競争入札
一般競争入札とは、国や地方公共団体などが行う公共事業の発注の時に工事概要などを公告して発注者側の条件を満たす希望者同士で競争して契約者を決める方式です。
指名競争入札
指名競争入札とは、国や地方公共団体があらかじめ指名した事業者のみで競争入札を行う入札方式のことです。
指名競争入札では、発注者が入札参加者の選定の段階で入札に参加できる者を指定や指名します。
発注者は受注希望者の能力や信用などを指名の段階で判断して、疑いのある者を入札執行前に排除することができます。
随意契約
随意契約とは、入札やせり売りなどの競争によらずに、適当な相手を選んで結ぶ契約のことです。国や地方公共団体が公共事業や備品調達や外注などで行う場合があります。
特定建設業許可
一般建設業許可を取得したあとは、特定建設業許可に切り替えるというように、元請として、規模の大きい工事を受注するには、一般を特定に切り替える、般特新規申請をする必要があります。
特定建設業許可は、建設業許可の一種で元請業者の取得は義務付けられています。この建設工事の額は消費税込みの額で、元請人が提供する材料等の価格は含まれません。
特定建設業許可の取得が必要になる場合
特定建設業許可が必要な金額については、令和5年1月の改正で「4.000万円→4.500万円(建築一式工事の場合、6.000万円→7.000万円)」に変更になりました。
建設業許可の更新
5年に1度の建設業許可の更新は、取得した建設業許可を切らさないために期限内の更新が必要です。
その時に、注意をしておかなければならないのは、許可要件の確認です。建設業許可の要件は、建設業許可を新たに取得する場合だけでなく、建設業許可を更新する場合も、審査の対象となります。
経営管理責任や専任技術者の常勤性を証明するための書類を準備しなければなりません。
更新ができないと、新たに建設業許可を取得しなおすことになりますので、期限が来る前に、事前に準備をしておきます。
決算変更届の重要性
建設業許可業者が必ず提出しなければならないのが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。
税務署に提出する決算報告とは違って、許可行政庁に提出する決算の報告です。
決算変更届の提出は、建設業法第11条2項に規定されています。
免除や提出を免れることはないので、法律に定められているとおり、事業年度終了後4か月以内に提出します。
業種追加申請
建設業許可の業種を増やす場合に必要になる申請が、業種追加申請です。
内装工事にとび工事を追加する、電気工事に電気通信工事を追加するというように、いろいろな組み合わせがあります。
業種追加の時に、問題になるのが、資格を持っている専任技術者が社内に常勤しているかどうかです。
資格を持っている人がいなければ、指定学科の卒業経歴のある人がいるのか、指定学科の卒業経歴のある人もいなければ、10年の実務経験を積んでいる人がいるのかというように、追加したい業種の専任技術者の要件を満たす人がいないかどうかを確認していくことになります。
建設業許可の事業承継
令和2年10月の改正で、事業承継(建設会社の合併・分割、事業譲渡、個人事業主の法人成り)の時に、建設業許可の番号を引き継ぎができるようになりました。
承継元会社の建設業許可を承継先会社が引き継ぐ場合は、事業承継の事実が発生する日よりも前に「認可申請」を行って「認可」を受けていなければなりません。
認可制度は、建設業法の改正とともにできた新しい制度で、事前に許可行政庁との打ち合わせや、事業承継と認可申請のスケジュールの調整が必要になります。